VMware Player で、Linux 上で Windows を使う ― 2006-11-25 17:50
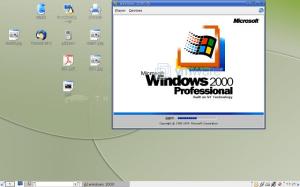
Windows とのデュアルブートが面倒になってきた。
Windows は、たまに MSAccess を使うときと、ウェブサイトの動作確認のときだけ使えればいい。そのためだけに Linux を落として Windows を立ち上げるのがたいへん億劫だ。
そこで、仮想マシンエミュレータの VMware を使うことにした。はじめて Linux をいじったころは VMware は有料だったが、無料版が去年リリースされていたのだ。すでに1年たっていて、かなりの情報も見られるので、思いきってチャレンジすることにした。
VMware Player を使い、SUSE をホスト、Windows 2000 をゲストにすることにした。
デバイスがホスト OS に依存することを考えると Windows がホストで Linux をゲストにするのが理想だが、通常は Linux を使うので、必要ない Windows がつねに立ち上がっているのはなんか気持ち悪いから。うまくいかなかったら逆にすればいいし、まあとにかく試してみよう。
まずは VMware のサイトから rpm を落としてきてインストール。そこまではうまくいったが、次に行う vmware-configure.pl の段階で、カーネルソースがないとか文句言われた。
ガックシきたが、とにかくググると Setting up VMware on SUSE Linux がヒット。どうやらパッケージが足りなかっただけみたいだ。当方のシステムには kernel-syms がなかったので YaST でインストール。しかしそれでも文句言われる。エラーメッセージを読むと今度は kernel と kernel-syms のバージョンが違うらしい。
少し悩んだが、バージョンの話なので、とりあえず YaST でアップデートしてみた。
すると OK。って、これも Setting up VMware on SUSE Linux の上の方に Warning が書いてあるじゃないの。最初からちゃんと読めよ、ということだ。
さて、VMware Player のインストールはこれで上手くいったようなので、あとは「VMware Player を導入してみました」を踏襲(多謝)。
自分は
# qemu-img create -f vmdk win2k.vmdk 4G
とした。なお、qemu は YaST にころがっていた。
vmx ファイルを書き、ゲストのインストールを開始。
しかしここで第2の関門が。自分の Windows 2000 はアップグレード版。以前のバージョンの CD を入れろと要求され、ここでアウト。CD を交換しても認識してくれないのだ。どうも vmplayer は稼働中に CD 交換ができないらしい。
さんざん考えて、いったん 98SE をインストールして、2000 にアップグレードすればいいことに気づいた。クリーンインストールしたかったけど、まあしかたない。とりあえず動くかどうかが肝心なのだ。
98SE のインストールは進んだが、今度は最初の再起動でつまづく。再起動したら真っ暗なまんま。なぜだろう。
その日は諦めてそのまんま寝て、次の日にふっと思い付いた。これは .vmx ファイルの記述が guestOS = "win2000pro" のままだったからじゃあないのか。最初に 2000 を入れようとしてたからそのままだったんだ。案の定、これを "win98" にしたら上手くいった。
で、98SE が立ち上がってからまた 2000 の入れ直し(というか、アップグレード)。これは思ったより早くすんだ。2000 は guestOS = "win98" のままでも動いたけど、いちおう "win2000pro" に戻しておいた。
以前の Windows の D ドライブはホストの Linux 側から samba で共有設定。ゲストの Windows ではドライブレター D でネットワークドライブに割り当てた。
これでほとんど native の Windows のように使えるはずだ。たぶん。
続いてディスプレイの設定。そのままだと 640x480 としょぼい。
上述の「VMware Player を導入してみました」のとおりに vmware-tools を入れたら、ちゃんと解像度も大きくなった。が、設定できるのは 4:3 の画面ばかり。自分のパソコンは Dell Inspiron 630m で、1280x800 というワイド画面だ。
ググったら、VMTN の Knowledge Base の KB1003 を参照しろという情報が。で、これがビンゴだった。
結局これはゲストの Windows のレジストリをいぢくればよい、というものだった。
情報どおり HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmx_svga\Device0. を開き、当方の環境には Resolution.10. まであったので「文字列」を選択して Resolution.11. を作った。で、値に 1280x800 を書き込んだ。
ゲストを再起動させ、画面のプロパティを開くと希望どおりに 1280x800 が選択肢にあり、きっちりと動いた。
これでおしまいと思いきや、Windows をフルスクリーンにして動かすと中央上部に VMware のツールバーがでてきて邪魔でしょうがない。
またしても情報探しの旅に出て、今度は VMTN のフォーラムにスレッドを発見。投稿者が混乱していて、読んでるこちらもつられて混乱してきたが、.vmx ファイルに gui.fullScreenAtPowerOn = "TRUE" を追加しろというカキコのとおりにしたら、VMware の起動時にツールバーなしでフルスクリーンで起動した。
と、いくつかてこずったところもあったが、導入は成功した。ディスプレイは、ウェブサイトの確認用という点では現在主流の 1024x768 の方が都合がいいので、結局 1280x800 はやめた。横に間延びしないで、ちゃんと両端が切れてくれるので確認用にはうってつけだ。

と、ようやく落ち着いたところで VMware Server も無料になっていることを知った。げっ、この方がよかったじゃん。でももう今さら変えるのメンドくさいから Player のままでいいや。
Lightbox JS をいれてみた ― 2006-11-16 00:21
調べものをしていてナイスな Javascript を見つけた。Lightbox JSだ。フラッシュみたいな動きで画像が表示されるのがなかなかカッコよくて、ひとめぼれしてしまった。
ウェブページはなるべく軽く、といつも思っているが、最近のパソコンは高性能だし、これくらいの仕掛けのページがいくつかはあってもいいかな、と弁解しつつ、ためしに先日 の仏像展のブログのエントリー と、こことかここ みたいな画像がメインのページに入れてみた。あんまり重くていらいらするようなら止めるかもしれないが、とりあえずはこれから徐々に増やしていこうと目論んでいるしだい。
導入は簡単だったが、loading.gif と closelabel.gif がリンクできなかった。が、これは CSS の方で http:// から始まる絶対指定にしたら上手くいった。また、ダウンロードしたオリジナルのものからディレクトリ構造を少し変えたほか、CSS で枠をつけたり背景を黄色にしたり、Mozilla/Firefox 用に角を丸めたりと少しいじってみた。
Lightbox JS のいいところは、ブラウザで Javascript
をオフにしていても、通常のリンクとして機能するということだ。クリックするとちゃんと画像が開くのだ。Javascript
をオフにしていてもストレスなくページが閲覧できるというのは大切だと思う。
また、今回使ってみた ver. 2.2
では、画像のグループ化とともに、キーボードで送り・戻し・閉じることができるようになっているのもいい。自分はどちらかというとマウスよりはキーボードを使って操作する
ことが多いので、こういう仕様は大歓迎だ。
しかし、やはりもっさり感はつきまとう。体感的には Firefox が一番速いように思う。IE はまあまあで、メインで使っている Opera が一番遅いようだ(泣)。また、Opera は現行の 9.02 だと画像にも opacity がかかって半透明になってしまうことがときどきある(泣)。Opera 側ののバグなんだろうと思う。
最大の難点はウィンドウサイズよりでかい画像だと画面からはみだしてしまうところだろうか。このままでは拙サイトのぐるぐる写真館
なんかには使えない。
と思いつついろいろ探りをいれると、やはり偉い人はいるもので、このスクリプトを改造した Lightbox
Plus というのが公開されていた。これ、画像の拡大縮小もできるし、マウスでつまんで動かせるし、おもしろくてたいへんいい。と思ったが、肝心の CSS
が思うようにいじれないので導入は見送ることにした。
句点で改行するブックマークレット ― 2006-07-23 11:38
いつの頃だったか、愛用ブラウザ Opera のカスタマイズ情報を検索していて、ブックマークレットの存在を知った。いろいろ漁って、結局今では次の2つを常用している。(リンクをクリックすると効果がわかります)
- サイトの更新時刻を表示する
- javascript:alert(document.lastModified)
更新日時で、そのサイトの情報の鮮度がわかる。私は、初めて訪問したサイトではホームが更新されているかたいていチェックしている。 - 句点で改行して文章を読みやすくする
- javascript:document.body.innerHTML=document.body.innerHTML.replace(/。/g,'。<br />');focus();
「。」で強制改行することで読みやすくする。しょっちゅう使っている。もうこれなしではネットサーフィンできない。元にもどすのにページを更新しないといけないのが欠点か。
いずれも Opera のツールバーに置いて使っている。
ところでブックマークレットはIEでは使えないもんだと思い込んでいたが、ひょんなことから使えることがわかった。そこで、句点で改行して文章を読みやすくするやつを、使い方とともに Home に掲載 するとともに、山行と旅行のページにスクリプトを置いてみた。自分はセンテンスが短いので、句点で改行するとまるで詩のように見えてしまい、あまりにも自分らしくないのでちょっとこそばゆい。
スクリプトを見て勘で分かると思うが、これは「。」を「。+ 改行」に替えるというモノ。つまり文章を変換できるのである。というわけで、
JavaScript:document.body.innerHTML=document.body.innerHTML.replace(/る。/g,'るのであります。');focus();
なんてえので遊んでみる。る。る。る。
ところで、IEの場合はちょっと問題がある。タグの中の改行コード(<br />)も解釈しちゃうので、たとえば画像へのリンクに「title="プラド美術館展。"」みたいに句点を使っていたりすると、タグの途中でほんとに改行しちゃって画像が表示されなくなってしまう。Firefox や Opera は平気なんだけど。
↓実験用。

Happy Hacking Keyboard Professional 2 ― 2006-04-21 00:48
欲しくてしかたなかった Happy Hacking Keyboard Professional 2 を買ってしまった。墨色の刻印付きモデル。
職場で、これまで同じシリーズの Lite 2 という廉価版の英語配列(PS/2接続)を使っていた。そんなわけで、もちろん Professional の存在は知っていたのだが、実物は見たこともなかった。web での評判を見るにつれ、一度触ってみたいなあと思っていたら、横浜のヨドバシに置いてあるのを発見。触ってみたらこれがまた感触が最高だった。
しかし Professional は PS/2 接続のモデルはなく、USB モデルだけだ。USBポートをひとつ占領されてしまうのはちょっとなあ、と踏ん切りがつかなかったのだが、3月に USB ハブ(しかも2.0)搭載の Professional 2 が新しく発売されたとあって、もう欲しくてたまらなくなった。
導入にあたっての最大の難関は矢印キーがないことだった。Professional では、Fnと右の小指のあたりのキーでカーソルを動かすのだ。矢印がないのはいくらなんでも不便だろう。Lite 2 でも同じ操作ができるので、矢印キーを使わないようにとりあえず練習してみた。
するとこれがなかなかいい。手をホームポジションから離さなくて済むので操作が速い。Fnを押す左の小指がちょっと窮屈な感じではあるがすぐに慣れてしまい、逆に、家のノートパソコンで矢印キーに手を伸ばすのが億劫になる始末。
これで導入に対する障壁はなくなった。で、ヨドバシのポイントがたまったのでとうとう買ったと言うわけだ。
で、家のノートパソコンにつないで早速使っているところ。かなり軽快な打鍵感。打ち疲れしにくそうだ。
Lite 2 とのキー配列の違いは矢印キーだけではなく、Spaceの左右のキー。左下にFnがない。そこで◇とAltを入れ替え、左◇(つまり本来のAlt)をFnに変更。これらの設定はディップスイッチでできる。これで使い慣れた Lite 2 とほぼ同じ配列になった。で、その左下のFnが Lite 2 に比べて自然なポジションにあるので窮屈な感じがしない。ただし逆にShift+矢印という使い方をするときがキツい。これは日本語変換をしていて文節を伸ばしたりするときのキー操作。ちょっと苦労するかもしれないが、まあまた慣れるだろう。
ちなみに、SUSE10.0 では、キーボード本体・ハブともに、バッチリ認識されている。
その後の、Inspiron 630m ― 2006-01-25 20:34
その後の、630m での linux の使用感。
イヤホンが使えない。夜中に音楽でも聴こうかとイヤホンをつないでみたがスピーカから音が出まくりで、イヤホンからは無音。ジャックの差し込みが甘いとかじゃないし、Win では使えるし。こりは困った。もう1週間近くネットで情報を探し回っているが、見つからないでいる。
愛用ブラウザ Opera で日本語入力ができない。どうも shared だといけないみたいだ。static をダウンロードしてインストールしてみたが、これだと日本語変換はできるようになるが、なぜかネットにつながらなくなってしまう(ローカルのファイルは表示されるのだけど)。
他の人たちはちははみんな上手くいってるみたいなので、自分だけ何か設定がおかしいのに違いない。ブックマークや設定ファイルは Win のものをそのまま持ってきてすぐに使えるので、どうしてもモノにしたい。標準のブラウザ Firefox に乗り換えようかもと思ったが、設定の面で痒いところに手が届かないし、どちらかというとマウスよりはキーボード派の自分には Opera の方が断然使い勝手がいいのだ。検索などは、とりあえず今はテキストエディタを使ってコピペしてしのいでいる。
バージョンを 8.51 から 9.00 Preview 2 に換えたら日本語入力ができるようになった。もちろん static 版。でも文字変換後に、入力語の前にカーソルが飛ぶという不思議モードだ(「ふしぎ」と入力し変換してから確定させると、カーソルが「議」の右じゃなくて「不」の左にいってしまう)。
左が温かい。パームレストの左手部分の温度が Win を動かしているときと比べて高いようだ。左パームレストの下には Express Card のスロットがあって、CPU も HDD も離れたところにある。分解してみたい衝動にかられる。
プリンタの設定は、USB で直につなぐのは簡単だった。ウチのプリンタは HP の 930c なのだが、USB ケーブルをポートに突っ込むと自動認識して勝手に YaST が立ち上がって設定開始。ドライバも SUSE には最初から入っていたので、Win よりも簡単だった。
にしても、linux の日本語入力の情けなさは定評があるけれど、さっき文を書いてて「伸びた」のつもりで変換したら一発目に「のび太」が出てきて脱力/// うわ、スラッシュでなかぐろ(「・」のことね)が出てこない! ちなみに IME は UIM-canna というやつです。Anthy のほうがいいのかしらん。Atok を買う気にはなれない。
Dell Inspiron 630m に Linux をインストール ― 2006-01-17 00:46

昨年暮れに購入した Inspiron 630m が、ようやく Linux でまともに動くようになった。試行錯誤の末、最終的にインストールしたのは SUSE Linux 10.0。
以前 Vine とか Redhat を使ったことがあったので、今回もまずはその系列のディストリビューションをインストールした。
まず Fedora Core 3 をいれてみたが、Fat32 のドライブが、マウントはできるものの ls で参照するとハングってしまう。これでは Fat32 のドライブを Windows と共有のデータ領域にすることができないので却下。無線LANも上手く動かなかった。
次に FC4。これはインストールはできたが起動ができない。ログを観察していると、どうやらサウンドデバイスを認識する段階でハングってしまうようだ。
そこで Vine 3.2 をいれたが、カーネルが古くて、内蔵無線LANの ipw2200 には対応していないようだ。
Turbo はCDイメージでの配布がないようなのでダウンロードが面倒。もう Linux は諦めようかと思ったが、ダメモトで未知のディストリビューションをいれてみようと思った。で、最初に試したのが SUSE で、これが当たりだったのだ。
インストール時の注意点はパーティション構成。いきなり「推奨構成」とかで、既存のパーティションを無視して Linux オンリーのまったく新しい構成にするのがデフォルトになっている。これではイカンので、構成変更。Linux 分として残してある10GBのうち、ブートを100MB、スワ ップを1.2GBほどとり、残りを ext2 にした。
Fedora なんかだと既存の Linux 領域だけを再構成するようにできるオプションがあって便利だが、SUSE では自分で設定する必要がある。Fdisk とかでパーティションをいじった経験がないと難しいのではないだろうか。
音は勝手に認識。Knoppix でもダメだったので、ちょっと感動した。MP3も問題なく再生するが、びっくりしたのは iPod 用に AAC でエンコードした音楽が再生できたことだった。そういえばインストール中のスライド画面にも iPod とも連携OKみたいなことが書いてあった。
反面、動画は MPEG すらダメだったが、これは別途 Xine をダウンロード、インストールすることで解決した。ただし VR モードで録画した DVD-RW が読み取れない。VR モードの RW は、標準で入っているプレイヤー Kaffeine で見られるようになった。たしか最初は見られなかったような? dvd::rip とかあれこれ入れたりしたせいだろうか・・・
音声のみならず、ハードウェアの認識はすばらしい。スマートメディアのUSBリーダ/ライタをぶっ刺してもきっちり認識してくれるし、その後の動作まで聞いてきたりして、まるで Linux じゃないみたいだ。
Windows 領域も勝手に認識してマウントまでしてくれる。デスクトップにある「マイ・コンピュータ」をクリックすると、その中になんとパーティション毎にディレクトリができていた。
ルートに「Windows」というディレクトリが出来ていて、そこにマウントされていた。
日本語名のファイルもバッチリだ。
無線LANは、快調に動いている。
ipw2200 のドライバは SUSE に元々入っている。最初動かなかったが、dmesg してみたらファームウェア関連でエラーが出ているようだったので、ログにあった version 2.3 をここから拾ってきて解凍、出てきたファイルを /lib/firmware にコピー。再起動したらあっさり eth1 で動いた。
しかし今度はAPに繋がらなくてハマる。WEP が違っているんじゃないかとかさんざんいじりまわしたが、eth0 を ifdown したらOKだった。eth0 の方が優先されるみたいだ。
Windows 同様、Fn + F2 で ON/OFF することができるのが地味に便利だ。
モニタの設定もハマった。630m は 1280x800 というちょっと変わった画面サイズなのだ。
この変則サイズを表示させるには、855resolution
を拾ってきてインストール。このへんのやり方は検索すればいっぱい情報がある。で、インストールしたら、コンソールから su になって/etc/init.d/boot.local というファイルに "/usr/sbin/855resolution 58 1280 800" を書く。再起動したら見事にワイド画面になったのだった。
というわけで、ド素人でもなんとか無線LANでネットができるまでになった。これで Windows ともおさらばできるかと思ったが、MSAccess で記録しているワインのデータが OpenOffice と互換できないようだ。それに、ウェブサイトなんかを持っている以上は Windows での動作検証は欠かせない。しかたないので Windows は残しておこう。
Dell Inspiron 630m 購入 ― 2005-12-24 22:38
メインPCとして、Dell の Inspiron 630m を購入した。
5月だったか、メインで使っていたイーヤマのノートPCが壊れてしまった。それからずっと、サブのNECのノートを使っていたのだった(これが愛用のブラウザ Opera と相性が悪いのか、しょっちゅう落ちる)。
次に買うメインPCの条件として、
- A4ノート
- 英語キーボード
- CPU は Pentium M (セレロンはイヤだ)
この3つだけは譲れない。で、探してみると、英語キーボードが選択できるのは Dell か HP か東芝くらいしか見当たらない。Lenovo は英語キーボードにあとから換装することも可能だが、あの Esc の場所がどうしても馴染めない。エスケープするつもりで F1 を押してしまい、ヘルプ画面になるのはストレスがたまる(このときのヘルプの展開の遅いのなんのって)。Winがないのも痛い。
で、消去法で Dell になった。
- CPU:Pentium M 740 1.73GHz
- RAM:512MB x1
- HDD:100GB
- 無線LAN:Intel PRO/Wireless 2200BG
- 14.1インチTFT WXGA
- DVD+/-RW (DVD+R 2層書込み対応)
と、まあこんな構成で送料込みで13万円弱。ワイド液晶というのがどうもひっかかるが、キーボードと値段からすると他に選択肢がないようだった。それにチップセットがインテルなので、Linux とも相性がいいだろう。
以下は1週間使用してみてのインプレ。
デルのノートはキーボードがぺらぺらだという評判だが、打鍵感は思ったほど悪くなかった。想定の範囲内、というヤツだ。職場で使っている Happy Hacking Keyboard Lite 2 と比べてキーの縦幅が短いのだろうか、Enter を押すときたまに\(バックスラッシュ)も同時に押してしまうが、これはそのうち慣れるだろう。このバックスラッシュもHHKに合わせてBackSpaceに設定を変えようかと考え中。Caps Lock は速攻で Ctrl に変更した。また、AXキーボードドライバをあてた。これで右 Alt ひとつで漢字かな変換ができる。Space が若干右寄りにあるが、このキーを左で押すクセのある自分でも大丈夫。
音がむちゃくちゃ静かだ。それまでのNECがほとんどファン回りっぱなしですさまじい爆音を出していたが、寒いせいかほとんどファンが回らない。たまに回っても以前ほどうるさくなくて、リビングで使っていてもまったく気にならない。
液晶はそこそこきれいだと思う。可もなく不可もなく、という感じか。光沢液晶も選択できたが、自分はパソコンで動画を鑑賞することはまずないので、ノーマルのもので充分。ただ、画面は今まで普通のA4ノートを使っていた身としてはずいぶん小さく感じる。そりゃそうだ、同じサイズに1024ピクセル入っていたものを1280にしようというのだから。だからB5ノートで XGA の画面を見ているような感じがする。うーん、やはりワイド画面のモデルを選んだのは失敗だったか・・・
内蔵無線LAN は感度がいいのだろうか、今まで使っていたメルコのカードでは検知できなかった無線基地まで探してきている。
スピーカは、職場や家で今まで使ったことのあるPCの中では一番音がいい。音量を上げても割れない。逆に、レコードショップサイトの試聴ソースの音の悪さがひどく際立ってしまうという難点も。
我が家の愛用のHDD/DVDレコーダはパイオニアの DVR-710H(2年くらい前のモデル)。DVDマルチドライブは RW の相性があるのかなあと思っていたが、710H で VR 形式で録画したテレビ映像もちゃんと読み取れた。ちなみにウチの Inspiron に搭載されているのは NEC の ND-6650A というドライブだった。まだ Inspiron で DVD を焼いたことはないので、逆が可能かは不明。実は試しに焼いてみようとしたのだが、ハングってしまい上手くいかなかった。メモリ 512MB は映像編集には少ないのかもしれない。
パーティションは100GBでひとつだが、自分はシステムとデータ領域を別にしないと気持ちが悪いのでパーティションを分割することにした。分割には Knoppix (CD1枚だけで動くLinux) に入っている QTParted が便利だ(Windows の Partition Magic みたいなソフト)。Windows を7.5GB残し、Linux 用に10GB、残りを FAT32 にして Win と Linux の共通のデータ領域にする。また、Windows 領域の前に数百MBの何かの設定ファイルのようなものが置いてある領域があったが、これはそのままにしておいた。
で、やってみたら、Windows から見たデータ領域のドライブが E になっている。つまり、C ドライブの次が E になっているのだ。これは非常に困る。愛用ソフトのもろもろはファイルの受け渡しやらの設定がすべて D ドライブの絶対指定になってる。今までの環境から、フォルダごとそのままコピーして D ドライブに置くだけですぐ使えるようになっているのだ。これを全部書き換えるなんて気が遠くなる。ドライブレターを変更しようとしてもなぜか D だけ選択できない。
おそらく Windows 領域の前にあるあの設定領域が D で予約されているに違いない、と考えた。検索してみるとどうも要らないようなので、再び QTParted を使いその領域を削除。で、Windows に戻ろうとすると、今度は Windows 自体が立ち上がらなくなってしまった。消したパーティションの中にブートセクションでも入っていたのだろうか。仕方ないのでいったんパーティションをまっさらにしてから仕切り直し、Windows のインストールからやり直した。これでようやく FAT32 が D ドライブになった。
再インストールのとき、XP が嫌いなので 2000 にしてみた。しかし 2000 用のドライバが見つからない。そこで、付属の再インストール CD についている XP 用のドライバをあててみたらきちんと動いた。付属 CD のドライバは HDD 上に解凍して使う形式なので、これまた D ドライブに置いておいた。これで Windows の再インストールが必要になったときも楽できる。USB が1.1でしか動かないので焦ったが、これは 2000 を SP4 にアップグレードして、Windows Update からドライバを検索したらちゃんと 2.0 になった。
Windows 環境はひととおり設定し終え、今は Linux での Intel PRO/Wireless 2200BG の動かし方を研究中。
WEB制作関係のソフト ― 2004-02-06 00:19
使用中のソフトを紹介。いずれもフリーで、Win98SE、2Kで動くもの。
- ez-html
- タグ挿入タイプのHTMLエディタ。現在メインで使っている。
XHTMLが書けて、日本語対応で、フリーのHTMLエディタって、これしかないのでは。xyzzyというエディタ(というか多機能すぎて単なるエディタの枠を超えてますが)に拡張プログラムをくっつけても結構いけるが、このez-htmlの方が使い勝手はいい。
動作も軽いので、たとえば誤字を発見したときなんかは、さっと直して簡易FTP機能であっという間にアップロード、なんていう作業もサクサク。WYSIWYGじゃないんで複雑な表を作るのがちょっとたいへんだけど、まあでも、単純なもの以外には、表は使わないので別にかまわない。
今までタグをきれいに書こうなんて考えもしなかったけど、これを導入してから随分と意識するようになった。 - Grep and Replace
- 文字通り、grepして置換なわけです。つまり、複数のテキストファイルの文章から指定した語句を検索して、そいつを置換するというもの。もちろん、検索だけ、ということも可能。
ez-htmlにもgrepして置換する機能はあるが、サブフォルダの中身までは検索かけてくれないみたい。これならバッチリ。 - にゃんこFTP
- 指定した日付以降に更新されたファイルだけをアップロードするFTPソフト。それまでFTPはホームページビルダーをメインにしていたが、2003年5月にパソコンを買い換えたのを機に乗り換え。
アップロードしかできないので注意。 - RootFTP
- 「にゃんこFTP」は、いっぺんにたくさんのファイルをアップロードするには便利で速いけれど、純粋にアップロードに徹しているソフトなのでダウンロードができないし 、 サ ーバの中身を覗くこともできない。というわけで、そんな用途にこれを使っている。
Ghostzilla ― 2004-02-05 21:31
ghostzillaは、名前からも分かるようにMozilla系のブラウザ。
なんとアプリケーションの枠の中でこっそり見られるのだ。うっしっしっし。
たとえばエクスプローラを開いているときに使うと、ファイルがずらずら出てくるところにウェブページが表示される。ツールバーなどはエクスプローラのままだ。
で、カーソルを枠の外に動かすと元の画面が表示される。そんで、カーソルで左端-右端-左端の順に画面の端っこに触れると、またエクスプローラ内にブラウザが復活。
もちろん、エクスプローラじゃなくって表計算でもメールソフトでもOK。ボスが来たらさっとカーソルを外に出しちゃえばいいんです。
画像や文字の隠れ具合のレベルを6段階に設定できる。レベルによって、カラー/モノクログレー、画像を常に表示/マウスを置いたときだけ表示、と変わる。グレーで画像隠してるととてもネットしてるように見えません。
日本語版はたぶんない。Win98SE、2K、XPで動作確認済み。